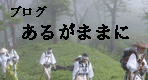| ・吉野山人雑文集 ・吉野山人運気情報 ・吉野山人プロフィール |
|
■吉野山人雑文集 |
4.世界遺産と吉野大峯 |
| 紀伊山地の霊場と参詣道」の世界遺産登録について ~吉野大峯を中心に
-平成16年3月、『21世紀WAKAYAMA』掲載分より 今年夏、紀伊半島の和歌山・三重・奈良の三県にまたがる「紀伊山地の霊場と参詣 道」がユネスコの世界遺産に登録されようとしています。その登録の対象となるの は、修験道の「吉野大峯」と、神道と修験道の「熊野三山」、真言密教の「高野山」 という三霊場と、それらの霊場への参詣道、つまり「大峯修行道(大峯奥駈道)」 「熊野参詣道(熊野古道)」「高野山町石道」の三つであります。 本稿では筆者自身が多くの協力者と共に深く登録推進に関わった「吉野大峯」と 「大峯奥駈道」を中心に、熊野と高野も視野に入れつつ、「紀伊山地の霊場と参詣 道」の世界遺産登録がどう扱われるべきものなのか、どういう意義を果たすのかにつ いて、想うところを述べさせていただきます。 さて本題に入る前に一言。筆者への寄稿依頼は、昨年十二月に放映されたテレビ和 歌山制作の「世界遺産を活かした地域作り」という番組の中で、「世界遺産になった だけでは余り意味はない。なったことをどう活かすかということに視点が置かれるべ きである…」などと、偉そうに語った筆者の発言に注目して頂いたのが機縁となった と聞きました。いま思えば汗顔の至りですが、こういう機会を作っていただいたこと を大変にありがたく思っています。このチャンスを大いに活用させていただき、今回 の世界遺産登録の真の意義作りを、多くの人々と共有できればと願っています。 一九七二年にユネスコで世界遺産条約が採択されて以降、二〇〇三年現在で全世界 で七百五十四件が世界遺産に登録されています。ただし同条約の批准に二十年を要し た日本では、今回の「紀伊山地の霊場と参詣道」を入れてもわずか十二件を数えるに すぎません。こういう事情ゆえか、日本における世界遺産に対する認識というと、や やもすれば観光資源の開発や地域活性化にのみ力点が置かれる傾向があります。しか し筆者は番組中でも語ったように、登録に向けての活動を始めた当初から、世界遺産 になることがゴールではなく、平和を希求するユネスコ憲章に立脚した世界遺産の精 神をどう地域に根付かせ、登録の意義を作っていくかということが大切にされなけれ ばならないと考えてきました。登録を目の前に控えて、いよいよその意識を強くする 昨今です。 では今回の「紀伊山地の霊場と参詣道」の世界文化遺産登録にかけるわれわれの想 いとはなんでありましょうか。 お恥ずかしい話ですが、実はわれわれは、和歌山県が「熊野古道」と「高野山」の 世界遺産登録推進活動を何年も前から進められていることなど全く知りませんでし た。知らぬまま、奈良県で一番最初に「吉野大峯」の世界遺産登録を言い出したので あります。その後、紆余曲折を経て、奈良和歌山三重の三県協議会で三県合同しての 世界遺産登録推進の協力体制が築かれ、「吉野大峯」単体ではなく、「紀伊山地の霊 場と参詣道」として新しい枠組みが出来上がるのですが、それはさておき、われわれ が「吉野大峯」を世界遺産登録しようと思い立った目的は次の二点でした。 まず一点目は、世界遺産登録への活動を通じて、われわれ修験道が培ってきた歴史 的文化的価値が再認識される土壌を作りたい、という熱い想いでありました。ご存じ のとおり、明治初年に行われた神仏分離政策によって、廃仏毀釈の大ブーム。神仏混 淆を旨とする修験道は大弾圧を受けました。明治五年(一八七二年)には修験道禁止 令さえ施行され、壊滅的な打撃をこうむったのです。以後、徐々に復興を遂げている とはいえ、いまだいろいろな分野で修験道は正当な評価を受けられず、そのことが現 在もなお修験道全体の力を損なう原因にもなっているのです。去る平成十二年(二〇 〇〇年)は修験道の開祖と尊崇される役行者の一三〇〇年忌に当たりました。我が吉 野金峯山寺においても、二十一世紀に向けて修験道復活の機縁とすべく様々な取り組 みを行ないましたが、まだまだ不十分というしかありません。さらにさらに国内的に も国際的にも、吉野大峯の修験道や吉野山が持つ文化・歴史・自然価値の再認識を広 げたいと念願し、この年、世界遺産の登録推進を目標に掲げたのであります。 第二は吉野大峯の自然環境保全への願いであります。われわれ修験道の本分は、山 を拝み、樹を拝み、祈りの心を持って山々を登拝修行することであります。それは山 や森林の大自然を神仏の曼荼羅世界と想念するものでもあります。ところが近年、そ の肝心の根本道場たるべき大峯山脈の荒廃ぶりには、目を覆うものがあります。物質 文明の災禍がもたらす乱開発や、酸性雨災害・自然生態の激変による自然環境の荒廃 によって、連綿として修験の法灯を継承させてきた宗教文化とその歴史の舞台を喪失 する危機に瀕しているのであります。まさにそれゆえにこそ、ユネスコの世界遺産条 約に謳われた「普遍的価値を有する人類共有の遺産として、次代に守り伝えていこ う」という精神を拠り所に、世界遺産の登録を、千載一遇の機会として多くの人々の 力を集め、修験道をはぐくんできた自然環境の保全を目指して行ければ、と願ったの でありました。 世界遺産といえば、過去の事例を見る限り、地域活性化や観光客誘致の方に目を奪 われがちであります。残念ながら、それはまちがっています。本来は人類の所産であ る文化と、その母体である自然の両者を、全人類で力を合わせて保護しようという世 界遺産条約の基本理念こそ重視されるべきなのであります。吉野大峯や奥駈道の世界 遺産登録においても、安きに流れることなくこの理念をきちんと踏まえた取り組みを 望むものであります。 こうしてみると、先に述べた「修験道が持つ歴史的文化的価値が再認識される土壌 を培うこと」というのは、今回の「紀伊山地の霊場と参詣道」の全体に関わるキー ワードでもあると思われます。「修験道が持つ歴史的文化的価値」というのは、言葉 を換えれば四季の豊かな日本が育んできた多神教的世界観であり、吉野熊野高野に共 通する日本固有の精神文化であります。爆発的な流行をもたらした平安期の熊野詣 も、高野山で営まれた真言密教の曼荼羅世界も、実は修験道同様その根底には多神教 的世界観がありました。また日本固有の多神教的風土によって支えられる宗教文化そ のものでありました。 そもそも世界遺産の精神は、「諸民族が互いの文化や価値観を理解することで偏見 を取り除き、心の中に平和のとりでを築こう」とするユネスコ憲章の思想に根を持っ ています。この原点を思い起こせば、今回の世界遺産登録の目指すべき意義とは、日 本固有の多神教的精神文化の再認識を何よりも大切にすべきなのではないでしょう か。 神仏分離政策は修験道に打撃を与えただけではありません。有史以来、日本列島に 営々として育まれてきた多神教的世界観を、そしてそれを中核とする日本固有の精神 文化の崩壊をも招いたのです。日本は全国土の七割が山といわれています。縄文時 代、あるいはそれ以前から日本列島に住み着いて、営々と精神文化の営みを続けてき たわれわれの先祖は、山や大自然からもたらされる豊かな恵みの中で、多神教的風土 の歴史を積み上げてきたのであります。それゆえ、日本人一般の信仰は、元をたどれ ば、自然の中で日本古来の神祇も外国から来た諸仏も分け隔てなく、敬い拝むという 多神教的風土の大らかさに根ざしていたはずなのです。ところが、このような我が国 固有の精神文化は、明治の欧米化・近代化政策以降徐々に捨てられて顧みられなく なってしまった感があります。昨今の殺伐とした社会様相の中でますます人々の心が 荒廃する原因もまた、日本人がこうして民族のアイデンティティを喪失していった過 程の中にあるように思われます。 吉野大峯から熊野に至る紀伊山地一帯、吉野大峯、高野、熊野の三霊場こそは、神 仏宿る聖地として日本固有の宗教文化を最も色濃く今日に伝える貴重な文化遺産で す。異なる宗教の共生、自然と人間との共生という二重の意味で、世界遺産の精神と も重なり合うこの宝物をきちんと守り活かしてゆく。それこそは、真に豊かな日本の 国家を築くことにとどまらず、ひいては世界に対して共存共生の一つのお手本を示す ことにさえなり得るのではないでしょうか。 キリスト教やイスラム教のごとき一神教的な思想に基づいて、世界全体を一元的な 価値観に染め上げ、グローバル化することの末路は、二〇〇一年九月に起きた米国同 時多発テロ事件やそれに続くアフガン、イラク戦争などに明らかであります。そし て、この冷厳な事実に、いまや世界中が気付き始めています。むしろグローバル化の 対極として、吉野大峯、熊野、高野に象徴される山岳霊場が持ち得てきた多神教的 な、互いの価値観を認め合うという世界観の中こそ、諸宗教や諸民族が仲良く共生す るための鍵が存在すると確信しています。そして「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界 遺産として持ち得る意義も、これらの信仰が古代から現在に至るまで修行や巡礼の形 で絶えず実践され、今後も環境破壊と宗教対立に満ちた今日の世界に向けて数々の メッセージの発信し得るという点にあるでしょう。今回の世界遺産登録は何よりもそ のような視点から見つめて頂きたいと願うものであります。世界遺産を活かした地域 作りに際しても、経済的な議論以前にこうした精神的な視点をきちんと踏まえること が求められています。またそういう視点を持って日本の文化を世界に向けて発信して いくべきであり、同時に日本人自らが日本人が長い歴史の中で培ってきた日本人のア イデンティティを見つめなおすきっかけになってほしいと筆者は考えています。 最後にもう一点を付け加えます。 それは日本における世界遺産登録のプロセスであります。いままでこのプロセスは そのほとんどが文化庁や環境省、つまりは日本政府がまず国内の候補地を選定し、そ の後に各地元へ連絡がなされて準備作業が始まるというトップダウン式でありまし た。しかしながら今回の「紀伊山地の霊場と参詣道」は単なるトップダウンではあり ません。和歌山県やわれわれ吉野に住む地元の人間が意識を持って取り組み運動を発 展させてきた結果であります。正式に本登録が実現すれば、現在日本各地の名刹地で 行われている世界遺産登録運動の先鞭をなすものであります。それだけにその責任の 大きさも背負わなくてはなりません。したがって、安直な観光開発や地域振興に陥ら ないよう、心して取り組んで行きたいと思うものであります。 これは世界遺産登録を提出した者の一人としての責任であり、修験道という日本固 有の宗教文化の中で生を享けた筆者からの、世界遺産に関する提言と願いなのであり ます。 合掌 |