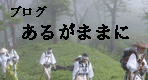| ・吉野山人雑文集 ・吉野山人運気情報 ・吉野山人プロフィール |
|
■吉野山人雑文集 |
3.役行者ルネッサンス宣言 |
-金峯山寺教学部長 田中利典 『大法輪』平成12年5月号掲載 
「役行者ルネッサンス」とは? 私たち人類は、この二十世紀に急速な物質文明の発展を遂げ、それによって日々の生活は便利になり、また多くの素晴らしいことが成し遂げられました。しかし、他方では、汚染による地球環境破壊や核戦争の脅威などといった、それに倍する多くの災いを生み出してきました。二十一世紀を目前にして、私たち人類は、この物質文明社会が導いてきた人類の繁栄と、そのほころびによる諸問題に直面しています。 今年は西暦でいう千年紀(ミレニアム)ですが、修験道にとっては開祖役行者神変大菩薩の一三〇〇年大遠忌に当たります。奇しくも、大きく行き詰まった感のある文明社会の区切りの年に、役行者の遠忌を迎えることは、修験道の持つ現代的意義を覚えずにはいられないのであります。 修験道は役行者以来、大自然を道場に、自然の中で人間が生かされていることを自覚しながら、一三〇〇年の法灯を伝えてきました。物質至上主義の現代社会にあって、今こそ、自然との共生といった在り様、人間力の高揚という実践による教えの力…等々、人間存在そのものを問い直す修験道の必要性を強く感じるのであります。 とはいえ、役行者及び修験道は、日本の宗教史・文化史においてそれほど高い評価を受けてきたとは言えません。古代における宗教的偉人といえば、聖徳太子や行基、空海などが挙げられますが、それらの偉人と比較して、役行者は知名度も低く、また修験道自身も猥雑な民間信仰としての位置づけに甘んじている部分がありました。とりわけ明治維新の神仏分離政策・修験道禁止の爪痕は今なお大きく、修験道の衰退に影響を与え、また正当な評価を受ける妨げにも繋がっています。 そんな現状から、現代に生きる修験者として、今年の役行者一三〇〇年大遠忌を機縁に、 1.役行者の歴史的位置づけを明確に示し、 という次世紀に向けての新たなる修験信仰の意義について発信していく、 こうした点を自覚するものであります。またその推進のためには修験道各派間の提携と連帯、つまりネットワーク作りの必要性も自覚するものであります。 さて、宗教は常に時代とともにあり、その時代時代に生きる人々への安心立命・癒しと救済を担って行かなければなりません。「ルネッサンス」とは再生であり、復興を意味しますが、私たちは、今年の役行者一三〇〇年大遠忌を「役行者ルネッサンス」と位置づけることで、役行者の正当な見直しやネットワーク作りを押し進め、修験道の潜在的可能性を大いに伸展させ、現代社会への癒しや救済という働きかけが果たされることを願っています。そしてそこには、繁栄の裏で、そのほころびに悲鳴をあげつつある現代社会にとって、次なる新世紀の進むべき方向を指し示すものがあると確信しているのです。「役行者ルネッサンス」を標榜することは、すなわち一三〇〇年の継続力をもって、次世紀への提言を始めようとするものなのです。 修験三本山御遠忌連絡会 役行者は大宝元年(七〇一)六月七日、摂津の国は箕面天上ヶ岳において、御年六十八才で、昇天されたと伝説されています。以来、一三〇〇年を経て、役行者を開祖とする修験道は赫赫たる伝統をもって現代に生き続けています。昭和五十九年、本山派修験の総本山聖護院では役行者の一三〇〇年遠忌を西暦二〇〇〇年に執り行うことが決定されました。続いて平成元年には、吉野のわが金峯山修験本宗総本山金峯山寺も役行者遠忌の執行を取り決めました。そういった遠忌に係わる動きと同時進行に、聖護院と金峯山寺、そして当山派修験の総本山醍醐寺の三者が中心となって、現代修験を紹介する『修験道修行大系』の編纂事業が始まりました(国書刊行会刊、平成六年発行)。加えて日本山岳修験学会の学術大会が、平成五年には醍醐寺で、平成六年には金峯山寺で開催されるなどして、『修行大系』編纂会議や学術大会準備会が相次いで開かれ、醍醐寺・聖護院・金峯山寺という、修験道のメッカ大峯山に深く関わる修験三本山が、同じテーブルに着いて話し合いの場を持つ機会を重ねたのです。 そんな中で、来るべき役行者の遠忌は、三山が合同してお迎えしようという機運が生まれてきたのは、役行者の深い思し召しと言わずしてなんでありましょう。役行者を共通の祖とする修験道教団といえども、三山の関係は必ずしも円滑で無かった時代も長く、三つの本山が共に手を携えて遠忌年をお迎えするというのは、初めてのことであり、かつてない大事件なのでありました。 平成八年夏、三本山合同による役行者展覧会開催計画の合意を契機に、三本山による御遠忌連絡会が発足しました。この連絡会は、今年二月で四十数回の協議を数え、この間、多くの共同事業が遂行され、多くの議論が積み重ねられてまいりました。 そのうち、三本山が主催者となり、昨年九月に東京・東武美術館で、十一月には大阪・市立美術館の二会場で開催された特別展覧会「役行者と修験道の世界」展は、延べ七十日間で、十万人近い参観者を集め、空前の大盛況となりました。併せて展覧会関連イベントとして、三本山合同大護摩供や役行者シンポジューム開催など、新しい三山の連帯活動も果たしたのでした。 また次世紀の大峯信仰を考えるという視点から、不可侵であった大峯山山上ヶ岳の女人禁制問題に関しても、大峯山の運営当事者である大峯山寺関係者に対して様々な提起がなされ、世間の物議を醸したことは記憶に新しいところであります。 今年の大遠忌本番には、三本山と大峯山寺による合同法要が、八月二十七日に山上ヶ岳において営まれます。これは修験道史上初のメモリアルな大法要となるでしょう。また同じく大峯山寺と提携して、大峯峯中・楊子宿の避難小屋再建事業も計画されており、正に修験道内の連帯と提携が形を持って果たされつつあるのです。 更に遠忌を記念して、三本山と近畿日本鉄道株式会社が発起人となり、今年二月に発足した「役行者ゆかりの三十九寺社集印巡り会」(参加寺社=聖護院・醍醐寺三宝院・金胎寺・笠置寺・瀧安寺・四天王寺・法楽寺・七宝滝寺・弘川寺・観心寺・千手寺・慈光寺・天龍院・興法寺・千光寺・宝山寺・霊山寺・松尾寺・室生寺・大野寺・当麻寺本堂・当麻寺中之坊・吉祥草寺・福田寺行者堂・転法輪寺/葛木神社・壺阪寺・世尊寺・龍泉寺・鳳閣寺・如意輪寺・竹林院・桜本坊・喜蔵院・善福寺・大日寺・東南院・吉水神社・金峯山寺・大峯山寺)は、役行者の遺徳顕彰と世間への遠忌広宣に繋がる大きな成果であります。これらの全ては「役行者ルネッサンス」に相応しい修験道内の新しい動きとなっています。 金峯山寺の取り組み 金峯山寺では五十年ごとの役行者忌を「遠忌」と呼び、百年ごとの年忌を「大遠忌」と呼んで開祖に対する報恩行を営んできました。が、今回の大遠忌は、単に金峯山寺一寺院の行事として行うのではなく、宗教的意義は保ちながらも、「新世紀に甦る修験の里、吉野に集う」という旗印の下、大遠忌法要や秘仏御本尊の開帳、各種慶讃イベントが行われます。この準備を通じて、地元吉野山や吉野町、更には奈良県など地域社会の人々や、他の関連する寺院、企業、文化人らとも提携協力関係を深め、役行者と修験道のネットワークづくりに役立つ取り組みを手がけてまいりました。そんな中から二十一世紀に向けて、「地球との共生」や「自然への回帰」「心の癒しと救済」などをテーマに、修験道が持つ大いなる可能性を世に問う「役行者ルネッサンス」運動の提唱が始められたのです。 具体的には金峯山寺を中心に、昨年九月に「役行者ルネッサンス一三〇〇in吉野」実行委員会(参加団体=金峯山寺・吉野町・吉野町観光協会・吉野町教育委員会・吉野町商工会・吉野山観光協会・近畿日本鉄道㈱・奈良交通㈱、後援団体=奈良県・(社)奈良県観光連盟・歴史街道推進協議会・(社)吉野青年会議所)が発足し、金峯山寺大法要に関連する各種イベントや奉納行事催行が決定しています。 しかしながら、このルネッサンス実行委員会の活動は、「役行者ルネッサンス」そのもの全体を指し示すものではありません。「役行者ルネッサンス」とは、ひとり金峯山寺や実行委員会に留まるものではないからです。ここまで縷々述べきたったように、役行者や修験道に関わる人々だけでなく、世の全ての人々に共通して認識されることを呼びかける事柄なのであって、ルネッサンス実行委員会や三本山御遠忌連絡会はその一翼を担うに過ぎないものでありましょう。 「役行者ルネッサンス」は遠忌年に始まりを迎えました。もちろん、この一年でやり遂げられる成果はそう多くは無いかも知れません。さりながら次の五十年、次の百年、いや次の千年紀に向けて、変革と再生への歩み出しになればと願っています。所謂修験道のバージョンアップです。そういう大いなる意識をもって、「役行者ルネッサンス」を広く世に宣言するものであります。 合掌 |