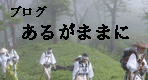| ・吉野山人雑文集 ・吉野山人運気情報 ・吉野山人プロフィール |
|
■吉野山人雑文集 |
2.朝日新聞/この人に聞く |
| -信仰の原点を見直す機会に(この人に聞く:田中利典さん) 朝日新聞奈良版 1999年12月27日 朝刊掲載 
「仏教庶民化図った ――役行者(えんのぎょうじゃ)とは、どんな人物だったのですか。 役行者の実体は史実からはつかみにくいのですが、きちっとした見直しが必要な方です。役行者が活躍されたのは、「倭(やまと)」から「日本」へ国家意識が変わった天武・持統朝のころです。聖徳太子、行基、弘法大師などメジャーな仏教者とは別の形で、役行者の宗教観なり、人物像なりは日本の歴史の底流に生き続け、修験道という形で現在に伝わっています。役行者は大和で活躍した人ですから、地元の人にもっと知っていただきたいと思います。 ――修験道をわが国の宗教史の中にどう位置づけますか。 日本の仏教の庶民化は一般に鎌倉仏教以後とされていますが、ちょっと違うのではないか。役行者は修験道によって、庶民の習俗に内在する山とか自然に対する神意識を伝来仏教の中に取り入れ、庶民化を図ったのです。道昭や行基が庶民の中に入ったり、空海が高野山に聖地を求めたりしたのも、修験道と同じ手法です。山岳信仰は平安時代に盛んになりますが、役行者はそのさきがけです。修験道は色々なものを採り入れて、独特の発展をします。 ――明治政府によって、神仏習合を基盤にする修験道は禁止されますね。 中世以来、全国各地にできた修験道の霊山のうち、英彦山(福岡・大分県)、羽黒山(山形県)、石鎚山(愛媛県)や大峰山系でも玉置山(十津川村)など多くは、神社で残りました。金峯山寺は一八八六年(明治十九年)に数少ない修験道寺院として仏教に復帰しました。以後、現在に伝わる修験道は仏教的側面の多いものになっています。でも、当方の主催する奥駆け修行に神主が参加する例も多いのですよ。 ――二〇〇〇年に役行者千三百年遠忌を迎える意義は。 百年前の千二百年遠忌は混乱期でしたが、今回は千年単位の西洋的な区切りと合致した節目を迎えました。修行はいつでもできるのですが、宗祖の遠忌はもう一度信仰の原点を見直すのによい機会です。修験道がもう千年、生き永らえることにつながるような遠忌にしたいと思います。 ――大峰山の女人禁制問題が話題になりましたが。 大峰山信仰を次の世紀にどうつなげていくかという課題の一つとして、寺院側から問題を投げかけましたが、信者団体の講社や地元も早急な結論は好ましくないという結論になりました。明治以後、各地の女人禁制が解かれましたが、きちっとした総括がされていません。修験道自体が存亡の危機にあったのに、大峰山の禁制だけがなぜ残ったのか、残ってきたことに意味があるという視点を忘れてはいけません。 女人禁制は信仰が生んだ慣習ですから、信仰を抜きにして考えるとおかしなことになります。山に登るというのは、異郷へ行くということです。女の人がいないというのは、非日常の世界で、これは修行の場所なのです。そういう所は寺院以前の問題で、信仰上は意味のあることです。そこをもっと見つめて議論してほしいと思います。 * 役行者は役小角(えんのおづぬ)とも呼ばれる。生没年ははっきりしない。伝説では、634年に茅原村(現御所市)に生まれ、葛城山で修行、金峯山上で衆生を救済する仏を求めて祈願、修験道の本尊の蔵王権現を出現させた。699年にざん訴されて伊豆へ流されたが、701年に放免されると神仙となって天空に飛び去ったという。旧暦6月7日が命日とされている。1799年に朝廷から神変大菩薩(じんぺんだいぼさつ)の尊号が贈られた。(奥村満富) |