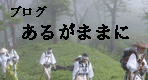| ・吉野山人雑文集 ・吉野山人運気情報 ・吉野山人プロフィール |
|
■吉野山人雑文集 |
1.役行者シンポジューム |
-平成11年10月9日に大阪で開催されたシンポジューム講演録
特別展覧会「役行者と修験道の世界展」(大阪展・平成十一年十一月二日~十二月五日開催)の関連イベントとして、修験道の意味を考える文化シンポジューム「スーパーヒーロー・役行者と修験道」(毎日新聞社・大阪市立美術館主催)が平成十一年十月九日午後二時から、大阪市天王寺公園内のマルチメディア映像館で開催されました。 まずシンポジュームに先立ち、宗教学者久保田展弘氏が「修験道の現代的意義」の演題の下に基調講演され、講演後、久保田氏を挟んで、醍醐寺の仲田順和執行長、聖護院の宮城泰年執事長、金峯山寺の田中利典教学部長ら修験三本山の代表や、展覧会を担当した石川智彦大阪市立美術館学芸員が演壇に上がり、役行者の教えや、現代社会に対して修験道が果たす役割、更には同美術館で開催される役行者展の魅力について話し合われました。 当日は三本山が一同に会しての初めてのシンポジュームということで、注目も集まり、一般の人を含めて約三百名の参加者がホール一杯に詰めかける中、内容的にも非常に密度の濃い討論会となりました。以下、基調講演の抜粋とシンポジュームの詳細を報告いたします。
【基調講演「修験道の現代的意義」】抜粋 私は最近、イスラム教やユダヤ教など、強烈な一神教の世界を歩いていますが、改めて修験道独特の世界観や宗教観について考えさせられています。一神教の地域では「自分たちと異なる宗教を激しく排除する」傾向があります。これに対して修験道は、祈りの対象が山岳という生命全体のありようであり、山岳を曼荼羅としてとらえています。礼拝者は、自然の森羅万象を肯定することになり、一神教の世界とは異なります。このことから私は、世界各地で起こっている様々な民族紛争にメッセージを発信しうる力を持つのが、修験道だと思っています。 修験道の世界は、文字化が遅れたため、日本の宗教史の中で正しく位置づけられてきていません。しかし千三百年にわたって「山駈け」が行われ、役行者の教えを受け止めてきました。日本人が、文字化されたものにしか、目を向けてこなかったことに問題があります。情報化社会だからこそ「浮世離れ」も必要ではないでしょうか。山駈けは、自分はどんな世界に生きるかを見いだす機会になります。他を否定するのではなく、「同じ生命」として存在を肯定し合える世界観を持ち続けた修験道は、日本民族の誇りと言えると思っています。
【パネルディスカッション】 司会:それではパネラーのみなさんを迎えて、パネルディスカッションに入ります。まずトップバッターの醍醐寺執行長の仲田さんに「役行者と修験道」というお寺の立場からの総論的なお話をお願いします。 仲田:醍醐寺の仲田でございます。役行者についてのお話ですが、修験道は、宗教的立場、仏教的立場からの歴史としては残っていません。そこで先人はどの様なことをしてきたかと申しますと、先ず、古典の中からそれを模索しました。最初に『続日本紀』の中に、役行者が水を汲ませたり、薪を採らせたりすることを鬼神を使ってこれを行い、もし言うことを聞かなかったら、その鬼神を呪縛したという記述があります。それが歴史、実在としてとらえられる記述です。その約二〇年後の『日本霊異記』の中にも、役行者の説話としてこれが取り上げられています。そしてそれ以降、時代を追う毎に『続日本紀』『日本霊異記』の中に書かれていることが、基調となってそれがだんだん膨らんでいき、役行者の一つの姿が現れてきているわけであります。そして江戸時代になって、修験道の教義、教化の資料として大成されるわけです。 役行者を語るとき、私は、『続日本紀』の中の、水を汲み、薪を採らすということが、当時の人々の一番大きな問題だったのではないかと思います。これを鬼神を使ってさせる、自分の手を使ってではなくて、ということに、私は非常に魅力を感じております。そしてやがて、空をも飛び、また『日本霊異記』の、山と山との間に橋を架けるように鬼神達に命じたという話、これらは私たちが今も持ち続けているところの願望ではないでしょうか。そしてそれらは、やはり今の社会においては科学と結びつきながら、橋が出来、水道が出来、ガスが出来、飛行機が飛びというような姿に結びついていくと思うのです。私は、この役行者の生き方、その姿の中に人間の本質を見い出し、そこに魅力を感じます。ぜひ、皆さまも『続日本紀』『日本霊異記』、さらには『今昔物語』などの古典をお読みいただければ、役行者のことが良く理解していただけるのではないかと思います。 もう一つ、修験道についてですが、私は現在、ごく身近に、多くの人が修験道の姿をしていると思います。皆さまもボーイスカウトの姿をご覧になることと思います。ホイッスルを持ち、ロープを付け、そしてコップをさげる。修験道の姿もこれらと何ら変わりございません。そこに私たちは、非常に安全性のある山に入る姿、行動的な姿を見い出して行くのです。 修験道の魅力は、お山に入って先ず修行をする。山懐に抱かれて修行をする。久保田先生は、曼荼羅という言葉でお表しになられました。曼荼羅の中心は大日如来でございます。大日如来の懐に抱かれながら、修行をする、山を巡るということです。山を巡るということは、実は心も一緒に動くわけです。私たちはお山の中で山懐に抱かれているという感を抱きながら、実は自分の心の中を馳せ巡るわけです。そこに、一つの生き方を見い出すわけです。森羅万象、全て我が師と感ずるわけです。その方法として、水の行、火の行、そして山に、大きな岩にしがみつき、風に吹きさらされながら、そして大空を仰ぎながら、いわゆる、地・水・火・風・空、これを文字ではなくて、自分の五感を通し、肌で感じていく。そしてその上に自分の意識、六大を築くということ、これが修験道の魅力の一つであります。 そして、全てのものを肯定しながら、進んでいくという姿には美しさを感じます。力の強い人は、力の弱い人に力を貸し、心迷う人には、その心を正しながら、一歩一歩山懐に入っていく。そこに、真の意味の平等、人の生命、人の生きる力、これの平等性を見い出しています。もちろんそこには全ての生きとし生けるもの、大峯山で表現するならば、男性のお山で、男性同士が自分の心の中に抱くものを育みながら、そして異性に対する気持ち、それはさらに、生きとし生けるものへと膨らんでいくわけです。稲村ヶ嶽で女性の方々が修行する時、やはり同じ心を抱いておられると思います。 今、世の中は平等という言葉が先行しております。その平等の陰で私たちは慈しみ合う心、助け合う心を忘れてしまっていると思います。これが修験道の世界で補われているのではないか、と考えている者の一人です。そして、生命の肯定も、私たちは、人が、身体が暖かい間は、そこに生命が宿されているのだという基本的な考え方を持っています。それは山では決して置き去りにしないという事です。修験道の世界の中で、山の修行をしている中で、遭難したということをお聞きになったことがおありでしょうか。私たちは、山の文化と里の文化をしっかり分けて、山に入ります。法螺貝の音によってお互い同士が離れてしまったか、高い所にいるか、低い所にいるかを知る。他の里の文化と比較したときに、トランシーバーや携帯電話を持っていけばいいではないか、とおっしゃるかもしれませんが、山には番地がございません。自分の居場所を他に伝えることは出来ません。これは私たちの普遍的なものの考え方です。 そして何よりも大切なことは、教えー教法、さらに全ての存在、そして自分の心の中に抱くところの霊性、この三つのことを総合的に大切にいたしております。先ほど久保田先生のお話の中で、一神教との世界がございました。一神教の世界でも最近、この三つに非常に近い言葉を主張しております。一つには、インテレクチュアル(intellectual知性な)という言葉、フィジカル(Physical身体的な)ということの大切さ、あるいはエモーショナル・スピリチュアル(emotional-Spiritual感情的、宗教的な)ということの大切さを説いています。それを総合的に実践されていくときに、真の人間の生き方があり、世界へこれが大きく発信できるものであると信じて、修行を続けております。後ほど、質問をお受けいたします。以上でございます。 司会:優しく、お話をいただきました。続いて、吉野金峯山寺田中さんには、山の中での修行を中心にしてのお話をお願いいたしております。宜しくお願いいたします。 田中:私は修験道というのは、非常に親切な教えであると思っております。久保田先生、仲田執行長からも修験道の修行についてお話がありましたように、いわゆる山伏というのは、山に臥し、野に臥して修行をするから山伏なのでありますから、山岳修行というのが修験道の修行の基本に在ると思います。我々は山を曼荼羅世界、神仏在す世界と見て入って参ります。「懺悔、懺悔、六根清浄」と唱えながら、修験者達が山を駈ける姿をテレビなどでご覧になった方もございましょうし、この会場の中には実際に修行しておられる方も沢山いらっしゃると思います。六根を清浄にして、神仏在す山に入り、神仏に近づいていく、自分を高めていく、あるいは神仏の世界には一度死んで生まれ変わって出てくる。擬死再生の修行とも申します。あるいは実際に自分自身の身体を使って歩くことによって何か気づきを得てくる…。 仏教の教えというのは非常に宏遠でいろんな教えが説かれております。例えば大乗仏教における最も大切なものは何かと申し上げますと、六波羅蜜行、いわゆる布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧という六つの修行が大乗仏教の修行の徳目でございます。ところが日常生活の中で、布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧、この修行が出来るかといいますと、凡夫である我々にとっては、日日の事柄に流されて、なかなか怠り勝ちであるわけですが、山に入りまして、例えば我々は吉野から熊野にかけて八日ほど山を駈けますが、その八日の中では、布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧という六つの修行が自ずから実践出来る。青色吐息の人に優しく声もかけられますし(布施行)、少々のことも我慢出来ます(忍辱行)。まじりっけなく、今日の宿所を目指して心専一に歩くことも出来ます(精進行)。あるいは歩く姿そのものが禅定に繋がる。「歩行禅」などと言われる方もおられますが、無念無想、サマーディーのような気持ちで、歩くことが出来る。 あるいは、教学担当という教団の仕事柄、よく人前で話をさせていただきますが、普段、娑婆の世界で法を説かせていただいても、しゃべっている方も、聞いている方も、どこか実感が伴わないこともありますが、山の中で毎日毎日共に行じながら修行しておりますと、一言一言の法話も、話をする方も素直に感じたままをお話することが出来ますし、聞いている方も素直に腑に落ちることがあります(智慧行)。そういった、大乗仏教における六波羅蜜行といった修行の徳目も、ただ机の上で学んでいるだけでは、簡単には実践に結びついていかないようなことでも、山の中で修行すると、誰もが実感出来る、そういうことが多々あります。 それから「仏道とは自己を知ることと見つけたり」というような言葉がありますが、日常の生活ではなかなか本当の自分に気づかない、自分と自分自身とが離れていると申しますか、自分を見失っている様な生活が在るわけですが、山に入るとまさに間近に自分と向き合います。たかだかこれぐらいの坂が、これぐらいの道が辛くなったときに、そこにいるのは、誰でもない自分であります。そういう自分に必ず出逢わせていただくことが出来ます。 ここで重要なのは、ただ山に登山で行くのではなく、山を曼荼羅世界とみて、神仏を拝む気持ちで歩くということです。我々は山に入りますと、石を拝み、岩を拝み、木を拝み、流れる川を拝み、空を拝み、風を拝みます。そこは久保田先生がおっしゃった通り、まさにあらゆるものを肯定しながら、歩かせていただく。しかも人間の存在を超えたものを感じながら歩くことが出来るわけであります。そういう意味ではどういう人であれ、その人なりに、大きな人には大きく、小さい人には小さく響く、そういう親切さが、山の修行、修験道の修行にはあるのではないかと感じております。 それと、現代の日本の宗教界、あるいは仏教界において、一般の人が門を叩いて、日常の生活そのままで、修行が出来る機会があるだろうかと考えたときに、修験道は、最高最大の修行と言われる奥駈修行でさえも、心有る方は、一般の人でも入っていただける機会を設けております。伝統教団の中で、一般の人が、平易に修行を共にする機会があるかと言いますと、なかなか敷居が高いのが実情ではないでしょうか。 最近、比叡山の千日回峰行者さまが、一日回峰と言うことで、一般の方を集めて修行をなさっておりますが、私はあれは修験道の修行だと思っております。回峰行というのはまさに修験道であります。修験道の修行でありますから一般の人も、敷居を低くして参加していただくことが出来る。そういう意味では修験道の修行は実践するときにも、実践に入る門口に立ったときにでも、常に親切であるのではないかと感じております。そういう機会が設けられておりますから、たくさんの方が毎年奥駈修行の参加を希望されております。実際には数も限られておりまして、皆さんどうぞと言うわけにはいきませんが、参加された一人一人の気持ちを聞いておりますと、なぜ皆さんが修行を望んで来られるのか、という姿が見えて参ります。 森岡正博というある高名な生命学者が、現在社会は無痛文明社会だということをおっしゃっております。文明社会がどんどん進んで参りまして、暑いときには冷房、寒いときには暖房、遠くへ行くときには車、飛行機。普段の日常の炊事仕事の中では洗濯機・掃除機・冷蔵庫など、我々の回りには本当に便利なもの、楽が出来るものが増えて参りました。そうしますと、肉体が楽をすることを優先する社会が生まれてきた。肉体が楽をするためにいろんなものを開発し、文明をすすめてきた結果、肉体が主になって、本来肉体の主であるべき心が隷属している社会が現出されてきた。これが無痛文明社会だと言われています。つまり、肉体を優先する社会というのは、物を優先する社会で、心が置き去りにされる社会でなのであります。そういう社会は、人間本来の生命(魂)がないがしろにされている社会であるとも言えます。そのような中で、修行に参加される皆さんは、何か現代社会の中で心が悲鳴を上げている、精神が何とかしたい、何とかして欲しいということを感じているのではないでしょうか。 先般、NHKスペシャルで金峯山寺と東南院の奥駈修行が全国に放映されました。次の日、金峯山寺も東南院も電話がパンクするほど問い合わせがありました。聞いておりますと、そう言った人たちの希望というのは、現実逃避ではなくて、今の息苦しい社会の中で、何か自分で前向きに変えていきたい、という気持ちをあの番組で感じて電話してきた、という方が沢山おられました。まさに、無痛文明といわれるような、肉体が精神を支配するような構造の中で、生命の反撃、反抗が始まろうとしている、そういう感じがいたします。 二十一世紀というのは、心の時代だと言われますが、まさにもう一度生命体としての人間、霊性を持った、物ではない人間としての生き方を模索しているのではないかと感じとれます。山に入りますと、肉体の痛みを感じます。肉体の苦しみを感じます。その肉体と自分の心が常に対峙して、常に葛藤する。しかもその葛藤が高まって参りますと、自分の存在を超えた、神仏や曼荼羅の世界というものが目の前に出て参ります。それこそ、本来の人間存在、人間の生命のありがたさ、肯定が始まるのではないかと思っております。 さて、二〇〇〇年には三山が互いに協力しまして役行者一三〇〇年の大遠忌をお迎えするわけですが、まさに二〇〇〇年というのは世紀の変わり目であります。世紀の変わり目に、無痛文明社会の中で悲鳴を上げつつある我々が、もう一度、歩み出しを始めるきっかけに、是非とも、役行者の持っている世界、修験道の持っている世界が生かされなけれならないと思っています。 修行の話からそれますが、金峯山寺では、来年にかけまして、「役行者ルネッサンス運動」を始めようと、取り組んでいます。私は気持ちの上で、今回の展覧会も、役行者という方をもう一度見つめ直して、新たな世紀に修験道を生まれ返らそう、あるいは新しく押し進めていこうという気持ちを持って取り組んでいます。いわゆる修験道のバージョンアップです。修験道はいろんな力、世界観を持っています。それは現代の閉塞された社会の中での答えを、沢山用意しているとも言えます。しかしながら、明治以来、修験道が廃仏毀釈によって禁止されたことによって、いささかその傷跡は尾を引いている感があり、遠忌を機会にもう一度新たに生み直そうという運動を始めたいと思っています。是非ともそういう機会に、この展覧会がなり、それから来年の遠忌年へと結びつくことを念じて、私の報告とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 司会:ありがとうございました。引き続き、宮城さん、お願いいたします。 宮城:私の立場は、もちろん修験者でありますが、と同時に、いささか学校で教鞭もとっております関係から、その立場も使いましてお話しいたします。 どなたもご存知だと思いますが、修験道というのは、古代の山岳信仰に拠るのでありまして、仏教渡来以前は、祖先の霊魂の行き着く先は神となる所、則ち山々が神々の住みかであって、岩、滝、そして草、水、森、すべてが神の顕現であるという事は先にもお話がありました。そして仏教の渡来により、それらが曼荼羅諸尊と変えられていくという事もすでにお話に出ております。そういう中で、山の人、シャーマン、霊力者の方に役行者がいらっしゃる、と位置づけております。そして役行者の活動が『続日本紀』を挙げてお話なりましたように、深く民衆と係わる宗教であった。その成立当初から民衆と係わる事が修験道の基本にあったと、位置づけられると思います。伝説の中の役行者が天性の霊力者であり、渡来系の民族である、そうした進歩的家系であった。しかも河内にあった万法蔵院を当麻へ移すとき、それが現在の当麻寺ですが、その土地を役一族が提供したという事から、背景には財力的なものもあって、役行者を取り巻く世界というのは、大きく人々から目を向けられていった。これが後の、開祖伝説のもとになると考えられます。道を作り、橋を架けるというのは、石橋伝説として残っておりますし、生駒の前鬼後鬼の折伏、ー役行者のお像を拝見いたしますと、前鬼・後鬼がついている形が多いですが、その折伏、あるいは五条北山に伝わる役行者の雨を止める伝説(展覧会図録解説参照)など、民衆の中で役行者が働いてきたことが、伝説となって残っている。その伝説の中には役行者の霊力が、もろもろの伝記の中から生かされてくる、ということが言えると思います。というのは、山の人が持つ力、官制の権力から生まれてきたものではなくて、庶民のレベルで、人々の悩みに応じる、それに応える能力がある。そうした力を畏れて、役行者時代以後、僧尼令などで僧が山に住むことを制限したり、あるいは私度僧を禁じたりしたのも、人々の心の中にそうした優婆塞・優婆夷、私度僧が深く深く、その活躍が浸透していったからなのです。その事は官権も畏れるものであろうと思います。権力というのは統制のもとにまとめていこうとするものですから。 平安時代以後になりますと、修験道も教団として、組織化されてきますし、そうした官制の宗教、官制の立場を背景に控えながら、庶民信仰をまとめていって、教団がまとまっていく様に位置づけられるのです。すでに修験者、験者、山臥というかたちで、平安の王朝文学の中にもたくさん出てくるほど、一般化していたのです。 江戸時代になると、そのような勢力が大きくなってきて、現在はこの三本山が一つになって役行者展を迎えておりますけれども、その頃は、本山派、当山派はいたって仲の悪い一時期があったという事も、一つの歴史的経過の中であります。しかし役行者を信仰する、修験道を実践する人々が、教団の後ろに沢山居てくれたから、ということが言えると思います。 その頃の修験者というのは、大峯に参って、山上ヶ岳本堂でお札を受け、そのお札を持って諸国へ行き、札配する、お札を配る。これは熊野牛王札を配るのと同じように、代参です。代参ということは、自らが、山伏達があの厳しい、今は交通機関が発達して楽に行けますが、家を出たときから厳しい道が待ち受けている山の上に行って、皆の代わりに辛い思いをして、しかも皆の代わりに先祖の神々の住んでいる山でお参りをする、そうした代参、代受苦、カードニックを受けてきたその徴としてのお札を配っていく。そのお札を配っていく中には組織上の権益なども出てくるので、地域の争いなども出てくるのですが、そうした代受苦の精神による宗教活動が、すでに中世の頃から修験者に大きくあった。 そして、明治維新になると、明治の時には権現信仰の廃止、修験道の停止ということが相次いで起こります。そうした時に、これは宮家準先生が詳しく修験道組織の研究の中でも述べていらっしゃいますが、政府と五条役所の圧力の中で、政府の監察使が派遣されて参りました野呂久左右衛門と、吉野一山が如何に戦いながら、修験を、或いは吉野一山の仏像を守ろうとしたか。寺院僧侶だけでなく、大峯に生きていた一山の民衆達が集まって陳情を繰り返し訴訟を起こす。そして修験信仰を途絶やすことなく、当時は神社になってしまった山上蔵王堂、現在の大峯山寺本堂、そして山下蔵王堂、現在の金峯山寺蔵王堂、ここの権現さんの前に降ろされた帳をかいくぐって、前に置かれた御神廟や幣束には眼もくれずに中の蔵王さんを拝んだ。それがやがて大きな力になって、明治十九年に修験道権現信仰は、自今勝手たるべき事という、政府のお達しが出され、一旦は廃止した修験道権現信仰についての、一応の訂正をするようになったのです。 その中で、山上ヶ岳に洞川から参る人たちが増えて参りました。そして、山上の本堂にある仏たちではなく、お花畑といわれる所に移された新堂の行者さんやその他の仏像にお参りをして帰る人が増えてきたところに、現在の洞川の繁栄、そして洞川の持つもう一つの悩みといった、いろいろなものが、今日までに原型として出てくるのだと思います。 このように見てまいりますと、修験道というのは、先ほども申しましたように、代わりに苦を受けるという民衆の熱烈な力によって支えられてきたことが、キーワードになると思います。その代わりに苦を受けるというのは、必ずしも山伏の世界だけではないだろうと思います。つまり、一遍上人や行基の貧民救済、一遍の癩病救済、或いは空也上人が自分も伝染病にさらされながらも、行き倒れの人たちを葬っていった、その裏側には空也上人などを支えていた一つの念仏集団があった。その支えによって、空也上人もあれだけの大きな仕事をなされていった。その空也上人に、知恵者で有名な?千観上人が「どうしてそこまで出来るのか」と問うたところ、空也は千観に「身を捨ててこそ」と応えたことが、『発心集』に出て参ります。そういう「身を捨ててこそ」ということを聞いた千観は、持ち物、きらびやかな衣を供に与えて、そして新たな修行に旅立って行ったことが出ております。 ですから私たち修験者というものは、山伏だけではなく、そうした人々の中にあって、苦を受けながらも、苦と如何に相対しながら、人々の幸せを願っているのか。先ほど言われました、六波羅蜜、菩薩行というのが、そこにあるわけです。菩薩の行いをするということが、次の二十一世紀というものへの位置づけだけではなく、これから生きていく上で、修験者が単に「大峯へ参った」「自分たちは今年も健康にめぐまれた、ありがたかったな」と言うだけではなくて、「身を捨ててこそ」という精神構造をもって、修行を続けるというところに、修験道の存在があるのではないか、と考えております。そういう点で、二十一世紀は、私は「身を捨てる」意識改革と見受けたり、というのを、結びの言葉にしておきたいと思います。ありがとうございました。 司会:ありがとうございます。引き続いて、石川さんに美術という点から、展覧会の見どころも含めて、お願いしたいと思います。 石川:今回の展覧会では、三五〇点ほどを、六つの章に分けて、展示しています。それでは、修験道の美術の特徴というものを掻い摘んでお話しします。 まず、初公開になります大峯山上の開帳仏です。今回の展覧会の見どころの一つです。それから、クリーブランド美術館の行者さん。これらは、岩座の上に腰を掛けて、両足を踏み降ろしています。これが倚像。山梨の円楽寺の現存最古の役行者像は片足を踏み降ろしています。これが、一般にいう半跏坐。これ以外にも、櫻本坊の像、金峯山寺の像の様に、いわゆるあぐらをかいている趺坐。他にも、江戸時代になりますと、普通に立ちました立像のお姿があります。役行者さんは、大きく分けても四つの像に分かれますが、これは、修験道の美術の多様性という事につながると思います。 第一章、役行者と修験道の祖師では、都合五五件が並びます。 第二章、蔵王権現の姿・形、こちらが五二件。その代表例である国宝の蔵王権現鏡像、こちらには一〇〇一年の制作の銘文があり、蔵王権現の中では、一番古い作例です。 それから第三章、修験の尊像ということで、蔵王権現を除く修験道の神さまや仏さまが、都合六七件並んでいます。例えば、兵庫県伽耶院の三宝荒神立像。これは役行者が感得されたお姿と言われております。それから、あまり聞き慣れないお名前かと思いますが、五つの眼をお持ちであります、宝起菩薩。こういった修験道ならではの尊像も並んでいるのも、今回の見どころの一つです。 次に第四章、修験の舞台ー曼荼羅、縁起絵の世界ーで、こちらは五八件あります。天川弁才天曼荼羅というのがその一つですが、真ん中の上の方にご本尊である弁天さんが描かれていますが、頭の部分が三つあり、三つとも蛇です。弁天さんと水の信仰というところで、蛇と繋がってくるわけですが、こういった非常に特殊な曼荼羅・尊像というものが絵画の方でも描かれる。この様な絵画が展覧会の主役に近い形で出るという事も、今回の展覧会の特徴です。富士山本宮浅間大社の富士曼荼羅は、上の方に富士山が描かれています。ご承知の通り、役行者さんは伊豆の大島の方に流されましたが、『日本霊異記』にもありますように夜な夜な海上を歩いたり、或いは空を飛んだりして、富士山で修行をしていたという事で、富士山も役行者さんに縁の深い地であり、各地の霊山の曼荼羅というものも出品いたしております。この章では絵画が中心になります。 それから、第五章、修験道の遺宝ー埋納・奉納の品々ーで、こちらは考古品が中心に三八件並びます。金峯山経塚からの出土品である金峯山寺や金峯神社所蔵の国宝の経箱類や、有名な藤原道長が西暦一〇〇七年に奉納した経筒などです。 最後は、第六章、修験道の歴史と信仰ということで、三〇件が並びます。例えば、板碑伝という、入峯入山の修行の証にするために木に刻んだもので、これは和歌山県熊野那智大社所蔵の、弘安四年(一二八六)に亀山上皇が那智の滝に参篭した際のものです。この他にも、先ほどからお話に出ています『日本霊異記』は平安時代の最古の写本(国宝)です。 この様に、大変さまざまな、多様なご宝物が出品されています。先ほど、それぞれの章において役行者像、蔵王権現像など多様性があると申しましたが、展覧会全体を見ても多様性に富んでいるというのが、今回の展覧会の見どころではないかと考えています。 順序が前後しますが、今回は役行者を主役に迎えたはじめての展覧会という事ですが、一四年前には奈良国立博物館で「山岳信仰の遺宝」という大々的な展覧会がございました。この展覧会と比べますと、今回の展覧会は、役行者さんと関わりのある霊山、お山を対象にしたもので、出品の幅という意味では多少狭くはなりますが、役行者さんを中心としていますので、そう言った意味では理解しやすいのではないかと、私は考えております。 それから、最後に修験道の美術の特色ですが、尊像、曼荼羅などに見られる、真言密教との関わりをこれまで、四先生方にお話をいただいたのですが、密教との関わりの中で、我々凡夫には大変理解しにくいお像が沢山ございます。例えば、先ほどご紹介いたしました三宝荒神、宝起菩薩、垂迹曼荼羅など、そうした秘義性の強い作品が出品されます。これらについても、なるべく分かり易く解説を施しているつもりですので、是非ご覧いただきたいと思っております。以上です。 また大変分厚い展覧会の図録を用意いたしておりますので、是非お買い求めいただいて、この機会に修験道の美術の方の知識も高めていただければと思います。ありがとうございました。 司会:石川さんは、三本山が一三〇〇年遠忌なので、来年の法要に合わせてこの美術展をやっていこうという話を出してこられるそれ以前から、個人的にも、テーマとしてこの問題を追っかけておられまして、データを集めておられました。ですから、非常に複雑なことを非常に簡明に、熱を込めて語っていただきました。 発言者の先生方も、まだまだ話し足りない、補足したいと思っていらっしゃるでしょう。金峯山寺の田中さんには行について、聖護院の宮城先生には歴史との係わりなどについて幅広くお話しいただいたので、皆さんも、ご理解を深めることが出来たと思います。 それでは、もう一言ずつ各先生方から、先ほどの話に補足するという形でお話下さい。 仲田:先ず、修験道を通じて行をするとき、先ずお金のことと学問と、それから生命を考えたら、これは出来ないということがあります。それから、私たちは山に入りまして、お互い同士、信仰というものは助け合うものであって、決して頼り合うものではない。信仰は助け合い、そして頼るものではない、ということを常々身にしみて入ります。どうぞみなさん方もご信仰というものを頼り合いになったときに、ご自分がどう思われるか、ということを心の中に置いていただければ幸いです。 田中:先ほど、次の時代は心の時代といわれていると言いましたが、我々は、菩薩の時代ではないかという事を申し上げております。菩薩というのは、六波羅蜜行に代表されますように、上には菩提を求め、下には衆生救済に赴くということ(上求菩提下化衆生)、つまり自分と他人とを分けないことが、菩薩なのだと教えております。人類が発展して参りましたけれども、まだまだ自分と他人を分けることに汲々としている時代が続いております。次の世代、次の世紀には是非とも、菩薩の時代、自他を分けないそういった時代が来ればという事を考えております。以上です。 宮城:その菩薩のことなんですが、仏教は基本に慈悲をもっていて、慈悲には差別がない。助けを必要としているものには、誰にでも、何処にでも、年寄であろうと、男女であろうと、常に働きかける精神作用というものを菩薩は持たなければならない。それが我々の行動の基本をなしているのだと、私も理解しております。そうでなければ、かつての聖達が、民衆の中で生命を懸けても弱者の救済には当たれなかったはずです。修験道というのは山へ入らなければ、ということになれば、体の弱い人、或いは入ることが出来ない人たちはどうするのか。菩薩というのは、私たちがこの世の中にあって、町にあって、人々の苦しみ、悩み、そして同時に喜びを共に分け合うことが出来なければ、その修験者の中にある代受苦の精神とは合致しないと思います時に、修験道はまた、里においても、非常に大事な基本を教えてくれるものだと考えております。以上です。 石川:先ほどお話しがありましたが、私は自ら役行者像オタクを自認しております。先ほど椅像・半跏像・趺坐像・立像の例を紹介しましたが、ほとんどが椅像であります。椅像以外の半跏像、立像、趺坐像を家で祀っている、あるいは何処かで見たとかということがございましたら、是非お教えいただきたいと思います。宜しくお願いいたします。 司会:石川さんはなかなか大した執念で、敬意を表します。さて、今日のシンポジュームでは基調講演として久保田展弘先生に、本当にいい話を、世界的な視野の中で、修験道の現代的意義ということをお話しいただきました。それを受けて、具体的な展開をパネルディスカッションの中で行った訳ですが、最後に久保田先生、補足ならびに締めくくりの様なことがございましたら、どうぞ宜しくお願いいたします。 久保田:もう、二〇年近く前になるかと思いますが、ブラジルで地球環境保護の問題をテーマにした会議などが開かれて以来、地球環境の問題などが各国で論議されてきました。さらに、日本でもこの二〇年ほど、エコロジーという言葉が、ある意味では形骸化するぐらい使われて、鎮守の森保護運動などが、どんどん展開されています。そういう広くは地球環境の問題というのが修験道の実践修養、山をどの様にとらえて実践していくかという事の中に、千何百年も活かされてきてるのだということに、私たちは、改めて注目しなければならないと思います。 それから、お互いにそういう実感をお持ちだろうと思いますが、現代はそれぞれお互いに一個一個の心の問題、悩みを抱いているわけですが、しかし、今にいたって、日本人にとって宗教というのが何か胡散臭い感じがする。宗教の在りよう、仏教の在りように対して、いろんな問題が出ていることも現実だと思います。しかしそれは、実に簡単なことで、やはり我々、娑婆の人間にとって、宗教者である人の背後に実践性が見えていない、ということが一番大きな問題だと思います。そういう我々が抱いている宗教に対する思いに、修験道という実践と一体になった宗教が、無言のうちに応えている。そういう意味でも修験道の、実践が現在にもっている任というものは、計り知れない意味があるのではないかと感じております。以上でございます。 司会:パネラーの皆さん、先生方、本当にありがとうございました。いいお話をいただきました。(拍手、拍手) |