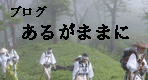| ■役行者 ■役行者ルネッサンス ・役行者ルネッサンスって何? ・大遠忌法要日程 ・秘仏金剛蔵王権現 ・法要の解説 ・大遠忌ポスター ・大遠忌報告 |
|
| 修験道の開祖である役行者の没後1300年に際し、今年の5月12日(金)から6月7日(水)まで、吉野金峯山寺を中心に、「役行者神変大菩薩千三百年大遠忌法要」が開催されます。 |
 |
「役行者ルネッサンス」趣旨私たち文明社会は、この20世紀に急速な発展を遂げ、日々の生活は便利になり、また多くの素晴らしいことが成し遂げられました。しかし、他方で、汚染による地球環境破壊や核戦争の脅威などという、それに倍する多くの災いを生み出してきました。21世紀を目前に、私たちは、この物質文明社会が導いてきた人類の繁栄とそのほころびによる諸問題に直面しています。 今年は西暦でいう千年紀(ミレニアム)ですが、我々修験道にとってはご開祖役行者神変大菩薩の1300年大遠忌に当たります。奇しくも、大きく行き詰まった感のある文明社会の区切りの年に、役行者の遠忌を迎えることは、修験道の持つ現代的意義を覚えずにはいられません。 修験道は役行者以来、大自然を道場に、自然の中で人間が生かされていることを自覚しながら、1300年の法灯を伝えてきました。物質至上主義の現代社会にあって、今こそ、自然との共生といった在り様、人間力の高揚という実践による教えの力…等等、人間存在そのものを問い直す修験道の必要性を強く感じるのです。 とはいえ、役行者及び修験道は、日本の宗教史・文化史において大きな足跡を残しながら、十分な評価がなされていません。古代における宗教的偉人といえば、聖徳太子や行基、空海などが挙げられますが、それらの偉人と比較して、役行者は知名度も低く、また修験道自身も猥雑な民間信仰としての位置づけに甘んじている部分がありました。とりわけ明治維新の神仏分離政策・修験道禁止の爪痕は今なお大きく、修験道の衰退に影響を与え、また正当な評価を受ける妨げにも繋がっています。 そんな現状から、現代に生きる修験者として、今年の役行者1300年大遠忌を機縁に、 1.役行者の歴史的位置づけを明確に示す という次世紀に向けての新たなる修験信仰の意義について発信していく、こうした点を自覚するものであります。またその推進のためには修験道各派間の提携と連帯、つまりネットワーク作りの必要性も自覚するものであります。 さて、宗教は常に時代とともにあり、その時代時代に生きる人々への安心立命・癒しと救済を担って行かなければなりません。「ルネッサンス」とは再生であり、復興を意味しますが、私たちは、今年の役行者1300年大遠忌を「役行者ルネッサンス」と位置づけることで、役行者の正当な見直しやネットワーク作りを押し進め、修験道の潜在的可能性を大いに伸展させ、現代社会への癒しや救済という働きかけが果たされることを願っています。そしてそこには、繁栄の裏で、そのほころびに悲鳴をあげつつある文明社会の、次なる新世紀に進むべき方向を指し示すものがあると確信するのです。「役行者ルネッサンス」を標榜することは、すなわち1300年の継続力をもって、次世紀への新たな提言をしようとするものです。 「役行者ルネッサンス」はこの役行者大遠忌年に始まりを迎えます。もちろん、この1 年でやり遂げられる成果はそう多くは無いかもしれません。さりながら次の50年、次の100年、いや次の千年紀に向けて、この1年が変革と再生への歩み出しになればと願っています。そういう大いなる思いをもって、「役行者ルネッサンス」を広く世に宣言するものであります。 合掌 |