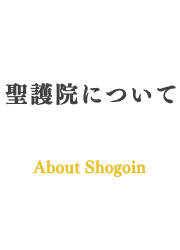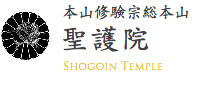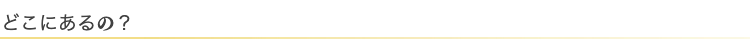
京都市左京区聖護院中町15番地にあります。
900年前に現在の場所に建てられましたが、4回の火災で市内を点々とし、今の場所に戻ったのは約300年前のことです。
明治までは西側に聖護院村があり、鴨川にかけてうっそうとした「聖護院の森」が広がっていました。
その森の中にある御殿であることから、「森御殿」ともよばれ、 今でも近所には聖護院と呼ばずに、「御殿」と呼ぶ方もあります。
この森の紅葉は、錦の織物の様に美しい為「錦林」と呼ばれ、 「聖護院」と共に今も地名として使われています。
聖護院の南西にある熊野神社は、平安時代に「聖護院の森」の鎮守として祀られ、 若王子神社、新熊野神社と共に「京の熊野三山」として崇敬されていましたが、 応仁の乱(1467)で焼失、1666年聖護院道寛法親王によって再興されました。
あの有名な聖護院大根や八つ橋はこの聖護院村で作られていたことから「聖護院」の名が冠せられたのです。
1734年11月16日、この森で呉服商の井筒屋伝兵衛23歳と、先斗町近江屋の遊女、お俊20才の心中がありました。
浄瑠璃作家の近松半二は、この事件をまとめ、「近頃河原達引」という作品、いわゆる「お俊・伝兵衛」を発表、現在も時折上演されています。
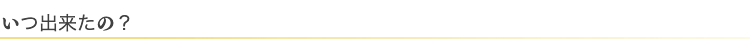
天台の第5代座主、智證大師円珍(814-91)が、 熊野那智の滝に一千日篭居をされた後、熊野より大峰修行を行われました。
その後大師の後を継ぎ、常光院の増誉大僧正が大峰修行を行われ、 修験僧として名をはせました。
この増誉大僧正は、寛治4年(1090)の白河上皇が熊野三山を参詣する熊野御幸に際して先達を務められ、その功績によって聖体護持の2字をとり、 聖護院という寺を賜ったのが聖護院の始まりになります。
増誉大僧正は、この時熊野三山検校職に任命され、 本山派修験の管領として全国の修験者の統括を命じられ、 聖護院の最盛期には全国に2万余の末寺をかかえる一大修験集団となりました。
この後上皇によって行われた熊野御幸の案内は代々聖護院大先達が勤め、 「伊勢へ七たび 熊野へ三たび 愛宕まいりは月まいり」と言われるほど、熊野詣は盛んになり、また愛宕山も修験の行場として栄えました。
後白河天皇(1156-58)の皇子、静恵法親王が宮門跡として入寺されてより後、 明治維新まで37代門主のうち、25代は皇室より、12代は摂家より門跡となられた皇室と関係の深い寺院です。
しかし応仁の乱で焼失、洛北岩倉へ移ったのですが再び火災に遭ってしまいます。
その後市内烏丸今出川に建てられた伽藍も延宝の大火で延焼、同4年(1676)に旧地に復しました。
現在の建物はこの時のものですが、役行者一千三百年御遠忌を記念し、 全国の教信徒の協力を得て数年をかけ修理、平成12年に完成しました。

聖護院は修験道の寺・山伏の寺です。
修験道に関係する仏様を多くお祀りしています。
役行者
前鬼後鬼・
大峰八大童子
本堂

役行者
宸殿
鋼造 出羽守政常作

宸殿壇上 不動明王
宸殿
鎌倉時代

宸殿左 不動明王
宸殿
江戸時代

宸殿右 不動明王
宸殿
室町時代

孔雀明王像
宸殿

蔵王権現像
宸殿
松久朋琳作

三宝荒神像
宸殿

逆手阿弥陀如来像
仏間


主として
・法華経(妙法蓮華経)
・不動経(稽首聖無動大威怒王秘密陀羅尼経)
・般若経、錫杖経を読みます。
しかし天台宗の影響を受け、法華懺法や例時作法(阿弥陀経)も日課としています。
修験道の思想からすると、宇宙一切の事象や音声は皆法身の顕れであると考えますので、
ありとあらゆる全て経でないものはないと考えます。


聖護院では次の様な行事を行なっています。

市内六千軒の信徒家々を回り、1年間の家内安全と息災長久を祈願する托鉢修行は、京都の冬の風物詩となっている。

寛政11年1年25日、宗祖役行者に、光格天皇より「神変大菩薩」の諡号を賜った事を記念し毎年法要が行われている。年賀式は古式にのっとり、末寺・信徒・講社先達が集い門主以下一山の僧侶と新年の挨拶を行う。

2日は堂内で柱源護摩が厳修され、3日は甘酒の接待、年男福女の除災招福の豆まき、採燈大護摩供が行われる。節分の御礼は厄除に霊験あらたかと多くの人が全国から受けにくる。

聖護院の開山増誉大僧正のご命日に法要を営み、報恩感謝を捧げる。

大阪・奈良・和歌山の葛城山脈に伝わる役行者法華経埋納地を巡拝する。例年加太・友ヶ島の行場修行、粉河町中津川行者堂での護摩修行、28の経塚のうち数箇所の参拝修行をしている。

役行者が大宝元年6月7日に箕面天井ヶ岳において昇天されて以来、この日を宗門の聖日と定め、高祖役行者の遺徳を忍んで行う法要である。
当日は茶道速水流宗派匠による献茶式、法華経三味供、採橙大護摩供など盛大に行われ、この日にご祈祷された御札は学業成就、身体健勝、家内安全等に御利益が有ると言われている。

大峰山脈の、吉野より前鬼までを縦走する修験道屈指の抖擻修行が大峰奥駈修行である。毎日約20〜25kmを約12時間かけて歩く。

智証大師は天台宗寺門派の始祖であり、大峰、葛城、熊野に修行し、役行者の法脈を受け継ぎ、修験道に天台密教の思想を取り入れ、本山派修験道の密教教学の祖とされている。
大師の命日(正当は10月29日)に法要を営み、御徳をしのび報恩感謝を捧げる。法要は奠供作法が声明と供に行われ、他に見られない独特の法要。当日は大師の御好物の品を添えた大師膳が申込者に出される。午後からは世界平和、除災招福を祈念し人々の幸福を祈る大般若波羅蜜多経六百巻転読法要が行われ希望の参拝者はお加持を受ける事が出来る。